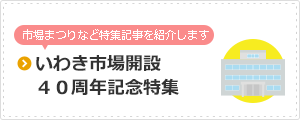だいこん(千葉)

- 品 名
- だいこん
- 品種名
- 青首だいこん
- 産 地
- 千葉県 JAちばみどり銚子野菜連合会
- 入荷時期
- 前年11月中旬~本年5月下旬
- 最盛期
- 前年11月下旬~本年1月下旬(秋冬)
3月~4月(春だいこん)
担当者からのコメント
全国一のトンネルだいこんの生産地を誇る千葉県JAちばみどり銚子野菜連合会より「秋冬だいこん」が出回っています。
銚子は千葉県最東端にあり、その南東部分は太平洋に面し、北は利根川沿線の低地、西は表層を関東ローム層で覆われた北総台地に連なって立地しています。海洋性の温暖な気候に恵まれ、昭和の初期からだいこんが生産されており、現在銚子では生産者数380名が650haを作付けしています。はやくから超低農薬、有機ブランド栽培に取り組み、生産履歴(トレーサビリティ)をはじめ平成15年には「もっと安心農産物」に登録、同時に「ちばエコ農産物」の認証を受けています。
出荷期間は前年11月から本年5月まで。2月から4月の春先には”さわやかだいこん”その他の時期は”銚子(灯台印)だいこん”の名で出荷されます。
だいこんはアブラナ科の1、2年草で日本では古くから各地でいろいろな品種が作られていましたが、現在では青首だいこんが全国的に普及しています。青首だいこんは地表に出ている部分が緑色になるので見た目がよく、適度な大きさで作りやすいことから全国に広まり、生食、煮物、漬物などいろいろな料理法に利用されております。
美味しいだいこんの見分け方としては、根の部分は白く、きめこまかく、張りと光沢のあるもの。茎の切り口に「ス」が入っていないもの。またひげ根やくぼみがなく、丸身が円形で持ってみてずっしりと重いものがよいでしょう。
だいこんは野菜の中で生産量、作付面積ともにナンバー1の商品です。健康的にも優れており旬の味としても欠かせない美味しい千葉産「だいこん」を是非ご賞味ください。
だいこんの効能
根部はビタミンC、葉にはビタミンA(カロテン)、B2、C、カルシウム、鉄分、食物繊維の宝庫で、肌を丈夫にきれいにし、便秘などにも効果的です。
また根に含まれているでんぷん消化酵素のジアスターゼとオキシターゼは炭水化物の消化を助けたり発ガン物質を分解したり、たんぱく質や脂肪の消化を助けるともいわれている健康野菜です。
だいこんの保存法
保存の適温は5℃前後です。
泥付きなら土の中もしくは新聞紙などに包んで暗い場所に、洗った物は適度な湿度を保つためにビニール袋、新聞紙、ラップなどに包んで冷蔵庫で保存してください。
新聞紙に霧を吹いておくとよいでしょう。
大根おろしは水気を切って冷凍保存しておくことができます。予め小分けにしておくと便利です。
■販売担当者
取締役 蔬菜第二部 部長
阿部 宏
秋冬はくさい(茨城)

- 品 名
- 秋冬はくさい
- 品種名
- 菜黄味(黄芯系)
- 産 地
- 茨城県 JA常総ひかり 八千代
- 入荷時期
- 前年10月中旬~本年2月下旬
- 最盛期
- 前年10月下旬~本年1月
担当者からのコメント
茨城県は全国一のはくさいの生産地、JA常総ひかりより「秋冬はくさい」が前年10月から本年2月にかけ出回っています。
生産地は関東平野のほぼ中央、茨城県の南西に位置し、年間平均気温14℃前後の温暖な気候と水はけの良い土壌で、その土には有機質をたっぷり入れ、また株間を広くとることにより栄養が全体に行き渡るようにしており、高品質で美味しいはくさいを生産しております。栽培品種は菜黄味といい、芯が黄色でジューシーで、軟らかく甘いのが特徴です。
淡泊な味わいがどんな素材にも合うはくさいは、外側の葉は汁の実や炒め物に、内側の葉は鍋物や漬物に、そして芯の部分はゆっくりと煮込んだりと丸ごと一個食べられて、料理に万能な野菜の代表選手です。
はくさいは約96%が水分ですが、ビタミンC、カルシウム、カリウム、鉄、食物繊維が豊富で、特に冬に不足しがちなビタミンCやミネラルの貴重な供給源になります。ビタミンCは風邪や美肌に効果的、カリウムは塩分を体外に排出するので高血圧予防に有効で、食物繊維が胃腸のぜん動運動を促し、便秘や大腸がんの予防にも期待できます。またはくさいはアブラナ科の野菜です。アブラナ科に含まれているジチオールチオニンは発がん物質を解毒する酵素の生成を促進し、がんも抑制してくれます。
冬本番を迎え、とくに鍋ものの恋しい季節を迎えます。鍋もの、炒め物、クリーム煮、スープ、サラダ、漬物などいろいろな料理法で健康的な旬の野菜、茨城産「秋冬はくさい」を是非たくさんお召し上がりください。
※こちらのJA常総ひかりのはくさいに関するホームページもご覧ください。
はくさいの保存法
冬場は丸ごと数枚の乾いた新聞紙に包み凍らないぐらいの冷暗所に根の部分を下にして立てかけておけば2~3週間は保存できます。使うたびに外側から1枚ずつはがして使い、冷蔵庫に入れてもじゃまにならないくらいの大きさになったら野菜室で保存します。
ちょっと変わった保存法としてざく切りした冷凍白菜は料理に重宝します。葉の部分を5cmくらいの大きさに切り、固めの塩ゆでにします。水気をしっかりときり、密閉容器で冷凍します。使うときは凍ったまま炒め物や煮ものに使います。2ヶ月くらいは充分持ちます。
美味しいはくさいの選び方
重量感があり、葉がしっかり巻いているものがよいでしょう。また根元の切り口が新鮮なものを選んでください。
カットされているはくさいの場合、切り口の中心部分が盛り上がっていないものが新鮮である証です。(中心部分は切られても成長を続けるため、時間が経つと盛り上がってしまうのです。)
■販売担当者
取締役 蔬菜第二部 部長
阿部 宏
親ばかトマト(いわき)

- 品 名
- トマト
- 品種名
- 親ばかトマト
- 産 地
- 福島県 JA福島さくら・いわき地区など
- 入荷時期
- 前年12月中旬~本年6月下旬
- 最盛期
- 1月~4月
担当者からのコメント
JA福島さくら、いわき市菊田施設園芸研究会より12月~6月にかけトマトが安定供給されています。
しっかりとした果肉と溢れるみずみずしさ、香り豊かでとびきりの甘さの「親ばかトマト」。
ここいわき市では太平洋に面した温暖な土地でこだわりの土づくりと人と環境にやさしいトマト作りをしており、平成14年には福島県特別栽培農産物の減農薬・減化学肥料栽培として認定されました。(認証シールを箱に貼り付けて出荷)本当に安全・安心なトマトとして出荷されています。
さて「親ばかトマト」のネーミングですが、実は「親ばかですが我が家の『自慢』のトマトです。」を略して名付けられたそうでまさにトマト生産者の自信作で、お薦めの商品でもあります。
西洋では「トマトが赤くなると医者が青くなる」ということわざがあるくらいトマトには様々な効能がありますが、特にリコピンは心臓病やガンの原因といわれる活性酸素を退治してくれる抗酸化作用があり、抗酸化力はベータカロチンの2倍、悪玉コレステロールの抑制効果もあります。また生で丸ごと食べられるので、熱に弱いビタミンCや皮の部分に多い食物繊維も効率よく摂ることができます。なんとトマト1個で1日のビタミンC所要量の40%の摂取ができるんですよ。
いわきの農産物にも指定されており、ミネラル豊富で健康的にも優れたパワーのある安全・安心な旬の美味しいトマト「親ばかトマト」を是非たくさんご賞味ください。
美味しいトマトの選び方
一般的にトマトはへたの緑色が濃く、ぴんと張っているのが新鮮である証拠。
丸みがあって重いものがみずみずしくて甘味も強いです。(水に浮かべてみると美味しいトマトは沈みます。)
トマトは野菜?果実?
かってアメリカではトマトが野菜か果実かで実際に裁判が起こってしまったことがあったそうです。トマトは植物学の分類では果実、 つまり果物とされていますが、日本の農産物の分類では「木になるのが果物」と決められているそうで、トマトは野菜に分類されています。
つまり果物とされていますが、日本の農産物の分類では「木になるのが果物」と決められているそうで、トマトは野菜に分類されています。
親ばかトマトについて
親ばかトマトについて詳しく知りたい方は、助川農園のホームページ(いわき市施設園芸研究会の一員です。)をご覧ください。
■販売担当者
蔬菜第一部 課長補佐
櫻田 竜一
春香うど(栃木)

- 品 名
- うど
- 品種名
- 春香うど
- 産 地
- 栃木県 JAなすの
- 入荷時期
- 前年12月中旬~本年4月中旬
- 最盛期
- 2月~3月
担当者からのコメント
栃木県のJAなすの管内においては土地利用型作物として、うどの栽培が盛んに行われており、とちぎ農産物マーケティング協会では地域ブランド農産物として認定しています。
初冬になると転作畑で養成していた親株を圃場から掘り起こし、地中に室(むろ)を作って根株を伏せ込み、白い芽を長く伸ばして収穫する軟化うどと、伏せ込んだ根株にもみ殻などをかぶせて芽を伸ばし、先端を光に当てて緑化する山うどの2つのタイプを生産しています。(山ウドの方が香りや渋みが強いそうです)
管内では大田原・那須地区などで主に山うどが生産されており、JAなすのでは「那須の春香うど」のブランド名で出荷。早いものでは12月から収穫が始まり4月くらいまで出荷が続きます。軟化うども大田原地区などで生産されており、春以降も根株を冷蔵庫で保存して徐々に伏せ込んでいくので12月頃から6月くらいまで出荷されています。
平成16年7月に4つの部会が統合し、新たな「JAなすのうど部会」を設立、全国最大規模のうど生産部会が誕生しました。
そのとき愛称を「那須の春香うど」と統一し、質・量ともに日本一のうどの産地にふさわしく「那須野の春のかおりを届けます」との思いを込めて名付けられたそうです。
うどは自生する山うどと栽培種があります。現在のうどは日本において野生種が改良され栽培された野菜で、日本が生んだ数少ない野菜の一つです。主成分は糖質と水分でビタミンやミネラルはあまり含みませんが、みずみずしさと特有の香り、またしゃきしゃきとした歯ごたえが美味しい野菜です。
さて、うどはとくに血の流れをよくして体を温める働きがあり、薬効につながる成分がたくさん含まれています。漢方では発汗、利尿作用、解熱、鎮痛に用いられており、強壮、神経痛、リウマチなどにも効果があるとされています。
この時季、春を伝える今が旬の美味しい栃木産「春香うど」を是非ご賞味ください。
うど(独活)の大木の意味?
風が吹いてもいなくてもひとりで動く植物だということから「独活」という字があてられました。「独活の大木」(うどのたいぼく)という言葉は、うどは自由に発育させると2mを越す大きなものになるが、大きくなったものは硬くて、味も悪く、食用にならない。身体は大きくても役に立たない人のたとえに使われます。ところで「うどの大木」なんていうけれど早い時期のうどは特に柔らかくて美味しい!。成長し過ぎると食べられなくなってしまうけど旬のものなら穂先は揚げて、皮は炒めて、茎は生でと余すところなく食べられる優れもの。昔から根を乾燥させて生薬としても使われてきたスゴイ奴なんです!
調理のポイント
うぶ毛を包丁でこそげてから適当な長さに切って皮をむきます。アクが強いので、さっと酢水にさらしたり、皮ごとゆでて水にさらします。生のまま酢の物やサラダにしたり、煮物や天ぷらなどのように火を通していただくなど様々な料理で味わうことができます。有効成分は皮のあたりに多いので皮はきんぴらにしたりなど捨てずにいただいてください。
■販売担当者
蔬菜部 常務取締役
熊沢 晃
秋冬ねぎ(いわき)

- 品 名
- ねぎ
- 品種名
- ねぎ
- 産 地
- 福島県 JA福島さくら
いわき市内出荷者
- 入荷時期
- 前年11月中旬~本年3月下旬
- 最盛期
- 前年11月下旬~本年2月
担当者からのコメント
今では一年中食べられますが、ねぎは冬または冬に向かう11月~3月の今が一番美味しい時季です。ねぎは気温が低くなってくると、甘みや風味が一段と増してくるからです。そこでいわき市の代表的野菜、重点作物にも指定されている「秋冬ねぎ」の登場です。
いわき市では100年以上前の明治初期から栽培が始まりましたがその後品種も変わり、現在では消費傾向から柔らかく、白根の長い、分けつの少ない高品質の「いわきねぎ」として約160haの栽培面積を誇り、生産量は約4000tと今では福島県一のねぎの産地となっています。
出荷形態はJA扱のものは5㎏箱(バラ・束)入り、いわき市内生産者のものは500g束と用途に応じて出荷されています。
さて、ねぎには様々な効能があり、ねぎ特有のツーンとくる辛みはアリシン(硫化アリルの一種)で血行を良くし、からだを温める働きや疲労回復効果のあるビタミンB1の吸収を促進する働きもあり、まさにこの時期、風邪の予防・治療に最適。また血液をサラサラにする効果や葉緑素、ビタミンC、食物繊維なども豊富に含まれております。
ねぎはご家庭でなくてはならない食材の一つで薬味や鍋物、焼き物、スープやサラダなど和・洋・中華料理全般に利用できる万能野菜です。特にこれからは鍋物の美味しい季節、健康的にも優れており、またいわきの特産品としても指定されている今が旬の野菜「秋冬ねぎ」をたくさんお召し上がりください。
ねぎの保存法
切ったねぎを保存するにはポリ袋に入れ、冷蔵庫で保存します。1本で保存する場合は湿らせた新聞紙に包んで冷暗所で保存します。泥付ねぎは、葉を出して日陰の土に埋めておくと長持ちします。
美味しいねぎの選び方
葉と白根の緑色と白色がはっきりしているもので鮮やかなもの。白い部分が長く、また張りと艶があって重たく、硬くしまっているものがよいでしょう。
ねぎの歴史
原産は中国西部、シベリアとされています。日本では奈良時代ごろから食用していたそうです。関東では白い部分を食べる白ねぎ、関西では葉の緑の部分を食べる葉ねぎが好まれていましたが、近年では料理に合わせて使い分けるようになっています。
■販売担当者
蔬菜第一部 副部長
小松 和徳
紅あずま甘藷(茨城)

- 品 名
- かんしょ
- 品種名
- 紅あずま
- 産 地
- 茨城県 JA茨城旭村
- 入荷時期
- 前年8月上旬~本年6月上旬
- 最盛期
- 前年10月~本年2月
担当者からのコメント
立春を迎えてもまだまだ寒冷が続くこの時季、とくに焼きいものが美味しい季節です。そこで全国でも有数のさつまいもの産地、茨城県JA茨城旭村より「紅あずま甘藷」が本格的に出回っています。
旭村は茨城県の東南部に位置し、東は鹿島灘、北は涸沼に面し、自然に恵まれた豊な純農村地域です。温暖な気候と水はけのよい酸素を多く含んだ圃場は甘藷を栽培するための条件にぴったり合っています。この恵まれた条件に加え、伝統ある優れた栽培技術が評価の高い美味しいさつまいもを育てます。
栽培されている品種は「紅あずま」。鮮やかな紅色で、甘みが強く、生食用甘藷の代表的存在です。焼いもやふかしいも、てんぷら等あらゆる調理法で美味しくいただけます。
甘藷は健康野菜の一つで主成分はエネルギーのもとになるでんぷんや糖質、その他ビタミンやミネラル、食物繊維などがバランスよく含まれており、たくさんの体によい効能があります。
中が濃い黄色の甘藷にはカロテンが含まれており、カロテンは体内に入るとビタミンAの働きをして体調を整え、がんの予防にも役立つといわれています。またカリウムも豊富で、体内の塩分バランスを調整することから高血圧予防に効果があり、ビタミンEは酸化脂質を抑え、老化防止に働きます。
さらに甘藷にはみかんと同じくらいのビタミンCが含まれています。ビタミンCは水に溶ける性質がありますが甘藷の場合は皮をむいても表面のでんぷんが加熱で糊化するので加熱しても6割以上が損失しないで残ります。そのため美容、風邪の予防、ストレス対策などに効果があります。食物繊維も豊富にあり、便秘、大腸がんの予防、美容などにも欠かせない野菜と言われています。
昔から「九里四里(栗より)うまい十三里)」といわれるほど美味しく健康的に優れている冬の味覚、茨城産「さつまいも」をぜひこの時季、たくさんお召し上がりください。
さつまいもが甘くなる理由
さつまいもが甘くなるのはでんぷん質にあります。でんぷんが糖化してどんどん甘くなっていきます。秋に収穫された時からゆっくり糖化しはじめ、糖化が止まることはありません。さらに水分が少しずつ抜けていき糖分が凝縮されていくのです。そのため秋から冬に食べていた美味しいお芋は春夏に向けてさらに甘く、美味しくなっていきます。
美味しいさつまいもの選び方
ふっくらと太っていて、皮がきれいでなめらかなものが良く、黒い斑点のないものを選びましょう。またひげ根の跡は小さいほうが良品です。また細いさつまいもよりは太いさつまいもの方が繊維質が少ないので味は良いでしょう。
さつまいもの保存法
さつまいもは寒いところが苦手ですから冷蔵庫に入れると「しもやけ」を起こし、黒ずんで痛んでしまいます。戸外で保存する場合も同様ですから12月を過ぎたら外に置かないようにしましょう。寒すぎないように、乾燥させないように新聞紙などに包んで、日の当たらない暗い所で保存するのが一番です。
■販売担当者
蔬菜第二部 課長補佐
星 優太
春キャベツ(千葉)

- 品 名
- キャベツ
- 品種名
- 春キャベツ
- 産 地
- 千葉県 JAちばみどり銚子野菜連合会
- 入荷時期
- 前年10月中旬~本年6月上旬
- 最盛期
- 前年11月~本年4月(春キャベツ)
4月~5月(新キャベツ)
担当者からのコメント
千葉県JAちばみどりより灯台印の春キャベツが10月から6月にかけ順調に出回っています。
同JAでは黒潮の恵みによる温暖な海洋性気候を生かし、昭和28年から作付が開始されました。昭和32年より「灯台印」の名称で出荷され、現在では銚子を代表する農産物として指定産地にもなっています。
産地では主として葉の柔らかさとみずみずしさ、また甘さで好評な春系キャベツが栽培されており、とくに春系品種「金系201号」の導入や栽培が難しい厳寒期収穫には耐寒性の強い「YR春系305号」などの品種を導入することにより、11月から6月までという長期出荷が可能となっています。さらに昭和50年頃からはキャベツの畝間にさらにキャベツを作付する「二番ざしの方法」が普及するようになり、作付面積の拡大が図られ、今では冬春栽培では日本一の栽培面積となっています。また産地では現在、環境にやさしい農業を推進しており、平成15年には農薬・化学肥料の使用は慣行の50%以下、生産履歴の記帳・開示など厳しい基準の「ちばエコ農業産地」の認証も受けております。
キャベツはビタミンCをはじめ、カルシウム、カリウム、ビタミンUなど豊富に含んだ健康野菜です。特にビタミンU(キャベジン)は胃潰瘍に効果があるといわれており、胃腸の調子を整える野菜として最適です。
キャベツは日本での栽培面積、収穫量ともにだいこんについで多い人気の野菜。いろいろな料理法にも対応できる万能野菜です。これからますます美味しくなってくる本場千葉産「春キャベツ」をたくさんお召し上がりください。
美味しいキャベツの選び方
春系キャベツは巻きが柔らかで弾力のあるもの、寒玉(冬キャベツ)は巻きが固く重量感のあるものがよいでしょう。また外葉が濃い緑色をしているものが新鮮です。
上部に割れ目が入っていたり、芯の切り口が割れているものは古いキャベツですので芯の切り口が新鮮なものを選びましょう。
キャベツの保存法
涼しい季節の保存なら、新聞紙などで包み冷暗所においても大丈夫です。
カット売りの場合は冷蔵庫の野菜室に入れ、できれば新聞紙や湿らせた紙でくるみ、ポリ袋で軽く包むとよいでしょう。
キャベツの名前の由来?
キャベツという名は英語の(Cabbage)。
キャベッジがなまったものです。キャベッジは頭でっかちをからかう古いフランス語カボシュからつけられたとのことです。
■販売担当者
取締役 蔬菜第二部 部長
阿部 宏
たらの芽(福島)

- 品 名
- たらの芽
- 品種名
- たらの芽
- 産 地
- 福島県 JA福島さくら ふたば地区
- 入荷時期
- 前年12月下旬~本年4月中旬
- 最盛期
- 2月下旬~3
担当者からのコメント
福島県JA福島さくら、ふたば地区より、春の訪れを告げる山菜の王様、たらの芽がこの時季出回っています。
たらの芽はウコギ科の落葉低木、たらの木の若芽で、奈良時代から高級な山菜として珍重されてきた野菜です。栽培ものは12月下旬から出回りますが天然ものは4~6月ごろ収穫できます。
本年産は現在のところ順調な生育となっており、特に2月後半から3月にかけ入荷が増すものと予想しております。
たらの芽は他の山菜に類のない特有の芳香と軽い苦味、ぬめりのある風味が特徴で、天ぷらなどの揚げものや浸しもの、また和えものなどいろいろな料理法で春の味覚を味わうことができる食材です。また健康的にも優れている山菜であり、サポニンと食物繊維が含まれているため、腸で糖質や脂肪の吸収を抑えるので糖尿病だけでなく肥満改善にも効果があり、血糖を下げる働きも持っており、さらにカリウムを多く含むので、むくみ解消や高血圧予防にも役立ちます。
また、たらの木の若芽であるたらの芽は、採取期間が植物の生長点にあたっているため、栄養価が非常に高く、薬効性にも優れているそうです。
健康的な山菜でもあり、山菜の王様とも天ぷらの王様とも言われる春の旬の野菜、福島産「たらの芽」を是非ご賞味ください。
たらの木と節分
陰陽道の考え方によると、節分は季節の変わり目にあたり、陰と陽とが対立して邪気を生じ、悪い病や鬼が横行する時とされて昔から豆まきなど「厄払い」が行われてきました。 鰯(いわし)の頭を柊(ひいらぎ)の枝にさして戸口に挿す風習は有名です。これは鬼が鰯の悪臭と柊のトゲを嫌うためです。
鰯(いわし)の頭を柊(ひいらぎ)の枝にさして戸口に挿す風習は有名です。これは鬼が鰯の悪臭と柊のトゲを嫌うためです。
ごらんのように野生のたらの木には幹に無数の鋭いトゲがあります。節分になると、柊とおなじく魔よけのためにたらの木を玄関に飾る風習がある地方があるそうです。
たらの木(芽)は、美味しいだけでなく霊験あらたかな木なのです。
■販売担当者
蔬菜第一部 副部長
小松 和徳